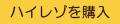原田和典の「すみません、Jazzなんですけど…」 第2回
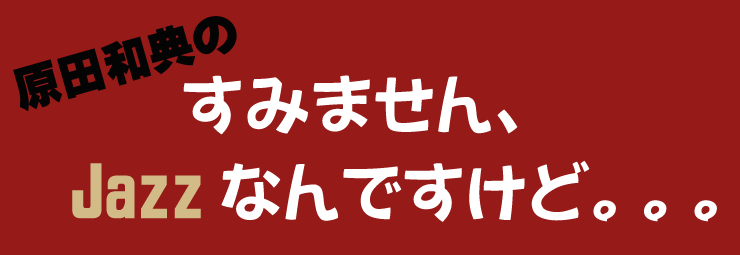
新年、どうぞよろしくお願いいたします。そちらも2016年になりましたか?
ジャズの楽しさ、面白さ、わかりやすさを、ひとりでも多くの方に知っていただきたい。こんなに素敵でヤバイ音楽を聴かずに死ぬのはもったいないではないか……そう思いながら雑煮を味わい、初もうでの賽銭箱に百円玉を投げたら釣銭も出ず膝もすりむかずという正月でございました。
が、スタート第2回目にして、テーマは緊急変更です。編集部のAさんからのお題はなんと、デヴィッド・ボウイの『★』!
たぶんCDショップではロックのコーナーに置かれていることでしょう。が、現代ジャズの中堅ミュージシャンがほぼ全編にわたってすさまじいプレイを披露しています。ジェイソン・リンドナー(キーボード)、ドニー・マッキャズリン(テナー・サックス)、ベン・モンダ―(ギター)、ティム・ルフェーヴル(ベース)、マーク・ジュリアナ(ドラムス)、マリア・シュナイダー(編曲)などなど、「よくこのメンバーに目をつけたものだ」と、ぼくはその慧眼に唸るばかりです。
★ (Blackstar) /David Bowie

では誰が慧眼を持っていたのか? ボウイ自身がニューヨークのジャズ・スポットをこまめに巡ってジャズメンたちに声をかけたのか? 違うと思います。ここ数年の彼は、もうすでに体調を崩していたのでしょうか、人前には皆無といっていいほど出ていません。カギを握っているのは、ボウイとは1960年代からのつきあいであるプロデューサーのトニー・ヴィスコンティでしょう。2013年、約10年ぶりにリリースされたニュー・アルバム『ザ・ネクスト・デイ』でも彼は辣腕をふるっていました。大変に充実したアルバムでしたが、トニーは“新しさ”という点にいささかの不満も持っていたようで、「新しいものを作るという意識で作ったのに、なにかしら過去の要素が入っていた」と述べています。そして「『★』は斬新で、まるで別の宇宙からやってきたようだ」と発言を続けています。
ぼくは2014年にシングル発売されたボウイとマリア・シュナイダー・オーケストラの共演「スー(オア・イン・ア・シーズン・オブ・クライム)」(本作の4曲目に収録)を聴き、「ジャズメンがロック歌手の伴奏をしている」のではなく、ボウイとインプロヴァイザーたちが混然一体となって“サムシング・ニュー”を作り出しているところに唸りました。そしてこの世界観をアルバム1枚に広げたら、空前絶後の傑作になるのではないかと夢想しました。そして今、手元に『★』があります。期せずしてボウイ最後のメッセージになってしまったこともあり、世界中で空前の売れ行きを示しているそうです。ということは、何千何万のひとの耳に、あのサックス・ブロウや、あの叩きまくりが届いているわけです。そのうちの1割が、ドニ―の『Fast Future』、マークの『Family First』など各メンバーのソロ・アルバムを買ってくれたら、それだけでもジャズ界全体のセールスは大いに上向きになるのです。
ぼくはロックも大好きですし、学生の頃は無謀にも「ロック・バンドで武道館に立って女にモテまくる人生」を夢見ていました。「スペース・オディティ」をカヴァーしたり、その関連で(というわけもないですが)BOØWYの曲もやりました。ボウイのアルバムでは『ロジャー』に鳥肌が立つのですが、「じゃあ君はロック側にいるのか、ジャズ側にいるのか」と問われた場合、過去の自分の仕事量における割合を顧みるに、「ジャズのひと」なのです。だからこのアルバムをきっかけに、ジャズそのものに対する注目がさらに高まってくれ、と心から願います。
参加者にだって、「この反響をジャズにフィードバックさせたい」という気持ちはあるはずです。別にこのアルバムをきっかけに、100%ロックに転身するミュージシャンがいるとも思えません。たとえばジェイソン・リンドナーは駆け出しの頃、ジャズ・ピアノの生きる伝説であるバリー・ハリス(今年87歳)に奏法を師事しました。小さな、30人も入れば息の詰まるようなジャズ・クラブで、4ビートのモダン・ジャズを熱く演奏しているところを、ぼくはかぶりつきで味わいました。が、そのままなら、グリニッチ・ヴィレッジの穴倉のようなライヴ会場を訪れたマニアックなリスナーの間で“すごい”といわれて終了です。エレクトリック楽器によるダンス・ミュージックにも精力的に取り組み、様々な分野のミュージシャンと交流し、いくつものプロジェクトで才能を発揮したことが、ジェイソンとボウイ側の距離を近づけたのでしょう。今や彼は、“David Bowie Keyboardist Jason Lindner”として世界的なカルチャー誌「ローリング・ストーン」のウェブサイトにロング・インタビューが掲載されるほどの存在になりました。数十人の前でしんねりむっつり、かたくなに旧式のジャズをやっているだけのミュージシャンに果たして、そんな機会が訪れるでしょうか?
ロック・ミュージシャンとジャズ・ミュージシャンのコラボレーションは過去、いくらでもありました。ロッド・スチュアートの一連の『ザ・グレイト・アメリカン・ソングブック』のように、“ロックの人”が“ジャズ関連の古典”を
歌う企画もずいぶん増えたような気がします。80年代半ばには、ポリスの無期限活動停止に入ったスティングが、ブランフォード・マルサリス、ケニー・カークランド(ともにウィントン・マルサリス・クインテット)、ダリル・ジョーンズ(マイルス・デイヴィス・バンド。90年代前半からはローリング・ストーンズ)、オマー・ハキム(ウェザー・リポート)とバンドを組み、目の覚めるようなサウンドを届けてくれたのも忘れがたいところです。ボウイもデヴィッド・サンボーンのサックスを採用したり(梅津和時はRCサクセションに関するインタビューで、「忌野清志郎と自分のコラボレーションは、ボウイとサンボーンのそれを参考にした」というようなことを語っています)、『アラジン・セイン』から『リアリティ』まで断続的ではありますがマイク・ガーソン(名門ジャズ・レーベル“コンテンポラリー”にアルバムあり)のピアノをフィーチャーしていました。が、それらは「ボウイのサウンドの中で、ジャズ系ミュージシャンが、それに当てはまるよう音を出している」という感じでした。でも、繰り返しますが、『★』はガチです。レコーディングがどういう手順で進んだのか(ジャズメンたちとボウイが一度でも顔を合わせたのかすら)不明ですが、個人的にはジャム・セッションの空気、やるかやられるかの殺気を強く感じました。
情報を入手して「これはすげえアルバムになりそうだ」と直感したぼくは無理を言ってこの作品を解禁前に聴かせてもらい、発売されてからも1日1回のペースで楽しんでいますが、とにもかくにも、デヴィッド・ボウイ氏は最後の最後に、ジャズに対してすごく嬉しい貢献をしてくれました。この恩をどう返していくか。「生きているジャズ」を追う者すべての課題だと思います。そして、今を呼吸するジャズメンの新作が、次々とハイレゾ化され、より多くのリスナーに届くことを願ってやみません。
■執筆者プロフィール

原田和典(はらだ・かずのり)
ジャズ誌編集長を経て、現在は音楽、映画、演芸など様々なエンタテインメントに関する話題やインタビューを新聞、雑誌、CDライナーノーツ、ウェブ他に執筆。ライナーノーツへの寄稿は1000点を超える。著書は『世界最高のジャズ』『清志郎を聴こうぜ!』『猫ジャケ』他多数、共著に『アイドル楽曲ディスクガイド』『昭和歌謡ポップスアルバムガイド 1959-1979』等。ミュージック・ペンクラブ(旧・音楽執筆者協議会)実行委員。ブログ(http://kazzharada.exblog.jp/)に近況を掲載。Twitterアカウントは @KazzHarada