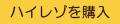原田和典の「すみません、Jazzなんですけど…」 第6回
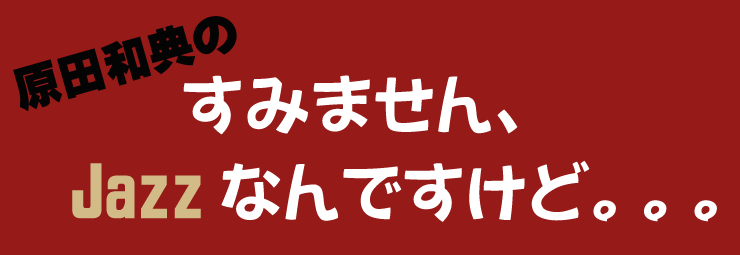
~今月の一枚~

Bob Dylan [Fallen Angels]
東京ってやっぱりすごい街なんだなと思います。去る4月、ボブ・ディラン、エリック・クラプトン、ブライアン・ウィルソン、アイアン・メイデンがほぼ同時に滞在していたのですから。
ぼくがディランに初めて感銘を受けたのは1983年下旬リリースの『インフィデル』というアルバムです(原題はInfidels)。もちろんそれまでにぼくは、ディランが“フォークの神様”と呼ばれ、日本のフォークやニューミュージック(と当時は呼ばれていました)のシンガー・ソングライターたちに影響を与えていたことを音楽雑誌などで知ってはいました。が、当時のぼくはフォークにさほど関心がなく(URCレーベルを聴いて驚くのはずっと後です)、RCサクセション、アナーキー、ザ・スターリン、ヴァン・ヘイレンなどのロックに夢中でしたし、YMOの“散開”にはクラスの音楽好きみんなで騒然となって、ジャズ関連もマイルス・デイヴィス復活の印象がまだ鮮烈だったり、ジェームズ・ブラッド・ウルマーや近藤等則や渡辺香津美が意欲的なサウンドを送り出していたりで油断できませんでした。それまでオリジナル曲中心に演奏していたキース・ジャレットが、突如“スタンダーズ”なる3人組プロジェクトでスタンダード・ナンバーを演奏し始めたのもこの時期です。ワールド・ミュージックという言葉がすでにあったのかどうかは記憶にありませんが、アフリカ・バンバータ、キング・サニー・アデなどもFMラジオからけっこう流れていました。この83年春、ぼくは初めて法事で東京に行き、札幌以上の都会が地球に存在するのだということを体感しました。
『インフィデル』を最初に聴いたのもFMラジオでした。スライ&ロビーという、当時めざましい勢いだったレゲエ界のリズム・チームが参加しているということがセールス・ポイントだったように思います。というのは番組のディスク・ジョッキーが、そこを強調して紹介していたからです。重く引きずるようなビートに、ディランのざらついた声が重なり、うねりにうねって中学生のぼくの心をつかみにきました。ファンキーだなあ、もう降参です。だからでしょうか、ぼくはディランに、ハーモニカホルダーをつけたアコースティック・ギターをかき鳴らし、社会的なトピックを盛り込んだ曲を早口で歌う、というイメージがあまりないのです。ただ歌声のよさ、サウンドのかっこよさにしびれ、好きになりました。初めてライブを見たのは1997年のことだったと思います。それからは来るたびに1公演は見ようと決めているのですが、いまにして思えばギターを弾いてオリジナル曲を勢いたっぷりに歌っていた頃のディランをもうちょっと多めに体験しておけばよかったな、という気持ちもあります。ここ数回の来日公演を体験された方ならご存知でしょう、十数年間、ディランはほとんどギターをプレイしていないはずです。そして鍵盤楽器を弾きながら歌うことが増えました……と書きたいところですが、先日の渋谷・Bunkamuraオーチャードホールのライブでは鍵盤もあまり演奏しませんでした。殆どの曲でステージ中央に立ち、スタンドマイクの前で朗々と歌ったのです。どんなオリジナル曲を? どんなグレイテスト・ヒッツを?
いいえ、演目はいわゆるスタンダード・ナンバー、ロックやフォーク界隈のファンよりもジャズ関連のヴォーカリストを聴きこんだひとたちが「うんうん」とうなずくに違いない楽曲が半数でした。もっとくだいていえば、フランク・シナトラやナット・キング・コールやビリー・ホリデイが歌っていたような、第二次大戦戦前から大戦後まもなくに書かれた曲のカヴァーが主です。「アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー」、「ザ・ナイト・ウィ・コールド・イット・ア・デイ」、「オール・オア・ナッシング・アット・オール」、「枯葉」。メロディをほとんど崩さず、スキャットを入れることもなく、ディランは朗々と、実に聴きとりやすい英語で明瞭に歌い込みます。「枯葉」に出てくる“winter’s song”という箇所、そこだけ急に音程が上昇するので、よほどの歌手でも最初に高めの音程をとって下がってくるか、もしくは低めのところから上に向けてグリッサンドするか、そのどちらかをとることが多いような印象が個人的にはあります。しかしディランはバッチリ、その音程に命中させました(少なくとも、ぼくの耳にはそう感じられました)。やり直しの利かないライブという場、しかも満員のオーディエンスの前で、ビシッと。なんという音感の持ち主なのだろう。なんというプロフェッショナルな歌うたいなのだろう。ゾゾッと鳥肌が立ちました。アイ・ラブ・ユーと心の中で叫びました。あの魅力的な声に、この音感。作詞作曲をしない、他人の書いた曲を歌う、いちシンガーに徹していたとしても、彼は歴史に名を残したに違いない。ぼくはそう確信しました。
新作についてのインフォメーションは、この執筆時点では皆無に近いのですが、前作『シャドウズ・イン・ザ・ナイト』と同じ時のセッションで、名エンジニアのアル・シュミットが録音を担当しているのは間違いないようです。11曲目「ザット・オールド・ブラック・マジック」の前奏にspliceの形跡がうかがえますが(ありえない速さでドラマーが、スティックからブラッシュに持ち替えています)、基本的には一発録りであるように聴こえました(編集部注:その後、正式に一発録りであることがアナウンスされた)。「スカイラーク」「イット・ハド・トゥ・ビー・ユー」など曲によっては低い音程のほうにメロディをフェイクしているところもありますが、それがレコーディングのその日その時のディランの“気分”だったのでしょう。枯れているのにやけに艶っぽい歌声、弦楽器を中心とした幻想的なバンド・アンサンブル。ハイレゾで入手し、ボリュームをあげて聴けば聴くほど、音の色気に魅了されるに違いありません。
ぼくは近年のディランに、“スタンダーズ”を始めた頃のキース・ジャレットをダブらせています。またキースはディランのファンで、キャリアの初期に「マイ・バック・ペイジズ」をカヴァーしたこともあります(もっとも、手本にしたのはディランの自作自演ではなく、ザ・バーズのヴァージョンのようですが)。その“スタンダーズ”も2013年、30年にわたる活動に終止符を打ちました。ディランの歌声とキースのピアノ、たったふたりだけのスタンダード・ナンバー集が制作されたらどんなに幸せだろう。それは永遠に叶わぬ夢なのでしょうか。
■執筆者プロフィール

原田和典(はらだ・かずのり)
ジャズ誌編集長を経て、現在は音楽、映画、演芸など様々なエンタテインメントに関する話題やインタビューを新聞、雑誌、CDライナーノーツ、ウェブ他に執筆。ライナーノーツへの寄稿は1000点を超える。著書は『世界最高のジャズ』『清志郎を聴こうぜ!』『猫ジャケ』他多数、共著に『アイドル楽曲ディスクガイド』『昭和歌謡ポップスアルバムガイド 1959-1979』等。ミュージック・ペンクラブ(旧・音楽執筆者協議会)実行委員。ブログ(http://kazzharada.exblog.jp/)に近況を掲載。Twitterアカウントは @KazzHarada