【プライスオフ終了】新イタリア合奏団の名盤がリマスター配信 &同時開催「弦楽器の響きを楽しむ8タイトル」プライスオフキャンペーン
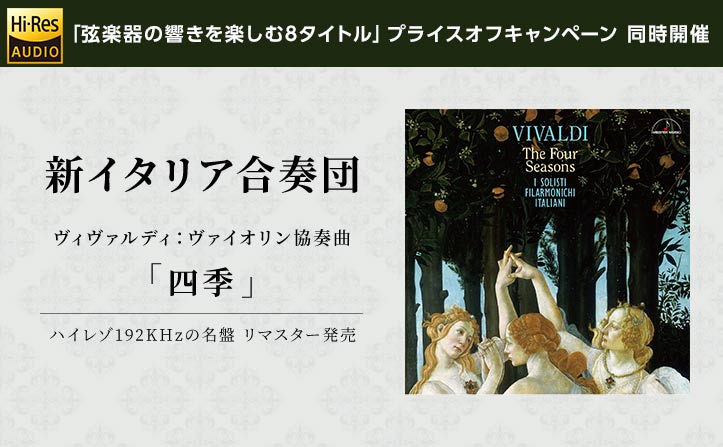
192KHzでレコーディングされた音源はアルバムとして2013年に発売されました。発売以来9年あまり、その
間のハイレゾ機器の進化は目覚ましいものがあります。そのため、情報量の多い192KHzの特性を生かした、
よりハイレゾの聴感に適するマスタリングを施しました。

アルバムについて <木幡一誠>
ちょっと時系列的にさかのぼってみよう。ここで秀逸な演奏を披露する新イタリア合奏団は、1979年に結成されたイタリア合奏団を引き継ぐ形で、新世紀を担うアンサンブルとして生まれ変わったものだ。その前身にあたるイタリア合奏団は、LP時代初期に気を吐いていた(年季の入ったファンには懐かしい名前にも違いない)ローマ合奏団の創設者、レナード・ファザーノの他界を受けて、その頃の在籍メンバーが組織したもの。そして当録音でソロを弾くフェデリーコ・グリエルモは、他ならぬローマ合奏団やイ・ソリスティ・ヴェネティでもリーダーをつとめていたジョヴァンニ・グリエルモの子息……。“弦の国イタリア”における、地の縁の深さと血の命脈の濃さを感じさせる話だ。
ここ20年ほどの間に、いわゆる古楽器系の団体を中心として、非常に自由度の高い「四季」の解釈が一般に浸透するようになった。もちろんそれは恣意的な自由ではなく、各曲に添えられたソネットの記述も踏まえながら、様式感に適う表現を多面的に試みた結果である。バロック音楽では不可欠となる即興的な装飾音形の付与はもちろん、譜面に書かれたフレーズの性格に応じた緩急や強弱の落差や、歌の線の伸縮もレトリカルな態度で付与していく。そんな解釈がモダン楽器にも波及し、単なる奏法や音響現象の猿真似ではなく、音楽の時代精神を生かす方法論として定着を見た。
その見事な成果がここに刻まれたともいえるだろう。地中海の陽光を感じさす明るい響きと、陰翳も豊かなカンタービレは「イタリアの弦楽合奏」という言葉から我々がイメージするものを最大限に具現化したものだ。そこに上記のようなアプローチが本当にセンスよく、過不足にならない絶妙な匙加減で加わる。「夏」を貫く気だるさや熱波の描写、肌を切る冷気を感じさせる「冬」の冒頭部分などはほんの一例。コンティヌオを受け持つチェンバロやテオルボによる和声的楽句の付与もときに大胆なほど饒舌だが(「秋」の第2楽章!)、不思議と音楽全体の調和を乱さないあたりに彼ら一流のインテリジェンスも感じずにはいられない。イタリアの伝統と今日的な美意識が幸福に手を取り合うヴィヴァルディ。赤毛の司祭もさぞかし満足だろう。
アントニオ・ヴィヴァルディ(1678-1741)
ヴァイオリン協奏曲集「四季」
1725年にアムステルダムの楽譜商シャルル・ミシェル・セーヌから作品8として出版された「和声と創意への試み」は、全部で12の作品からなるヴァイオリン協奏曲集。その第1番から第4番が「四季」の名で親しまれてきた。初版譜で各協奏曲に付された作者不詳のソネット(14行詩)の内容に基づき、後世の人間が与えたタイトルである。曲集全体はヴィヴァルディの庇護者にあたるボヘミアのモルツィン伯ヴェンツェスラウへの献辞を掲げているが、同地の宮廷楽団を想定して書かれたかどうかは疑わしい。1720年代初頭に完成したとおぼしき初期稿がドレスデンやマンチェスターで確認されており、そこに認められる異同も反映させた校訂譜による演奏が現在では一般的となっている。
後期バロックの合奏協奏曲の様式的集大成とも位置づけられる一方、ソネットの記述をなぞる標題音楽ないし描写音楽的な筆致が、トゥッティとソロの交錯するリトルネロ形式と巧みな融合を遂げた「四季」。そのソネットに関していえば、「春」や「冬」の第1楽章、あるいは「秋」の第3楽章のように、曲想の転換箇所ことに劇のト書きよろしく詩句が分割して配されたものもあれば、「夏」の第3楽章のように、音楽の描く内容を冒頭にまとめて記したものもある。以下、ソネットの概要をたどりながら各曲について触れておこう。
協奏曲 ホ長調 「春」 RV269 (作品8の1)
【I. アレグロ】 快活なトゥッティと共に春が訪れる。喜ばしげに挨拶を交わす小鳥たち。柔らかに波打つ楽句が泉の流れを表す。にわかに黒雲が空を覆い、春雷が轟き、稲妻がきらめく(急速な音階とアルペジョ楽句)。青空が戻れば、小鳥が再び嬉しそうに歌声を響かせてくれる。
【II. ラルゴ】 一幅の絵画を思わせる、花咲く野辺の情景。樹々の葉が風にそよぐ様子を描くヴァイオリンに対し、ヴィオラが断続的に奏でる音形は犬の啼き声。その番犬をかたわらに従えながら、しばし羊飼いは眠りに落ちる。
【III. アレグロ】 輝く太陽のもと、ニンフと羊飼が牧童の笛の調べにあわせて輪舞する。
協奏曲 ト短調 「夏」 RV315 (作品8の2)
【I. アレグロ・ノン・モルト―アレグロ】 猛暑が到来。熱波の中で人も家畜も憔悴し、松の木も燃え上がらんばかり。やがてカッコウの声が響き、山鳩とヒワが啼く。そよ風が吹くかと思えば(連続する3連符)、不意に北風が襲いかかる。バスの半音階進行を従えたソロは、自らの運命を嘆く羊飼の姿だ。
【II. アダージョ】 平穏を乱す稲妻や雷鳴、そして蠅の群にさいなまれて、羊飼は疲れた体を癒すこともできない。
【III. プレスト】 彼の恐れがついに現実のものとなる。雷鳴がとどろき、霰が降り、畑の穀物を容赦なくなぎ倒していく。
協奏曲 ヘ長調 「秋」 RV293 (作品8の3)
【I. アレグロ】 収穫を喜ぶ村人の歌と踊り。酔漢連中は足取りもおぼつかない(独奏声部の音階走句やトリル)。彼らは宴の果てに酔い潰れて寝転がってしまう(最後のトゥッティに先立つラルゲットの楽句)。
【II. アダージョ・モルト】 弱音器をつけた弦合奏が静かに弾き連ねるハーモニー。その神秘的で陶酔感を誘う空気に包まれ、歌と踊りに疲れた村人たちが甘い眠りについているのだ。
【III. アレグロ】 狩の情景。同音連打が鉄砲の音を描写。いったんは逃げた獲物も狩人と犬に追い詰められ、やがて力つきて地面に倒れ伏す。
協奏曲 ヘ短調 「冬」 RV 297 (作品8の4)
【I. アレグロ・ノン・モルト】 雪が降りしきる中を凍えながら進む。冷たい風が肌を刺す。思い切って足下を踏みしめ駆け出すが、あまりの寒さに歯の根が合わない。
【II. ラルゴ】 屋内では暖炉が燃え、それを取り囲んで満ち足りた休息の日々を過ごす。ピッツィカートの連続する伴奏音形は戸外で万物を潤す雨の描写。
【III. アレグロ】 氷の上に足を踏み入れ、滑っては地面に激突。立ち上がって激しく走り出せば、今度は氷が砕けてしまうほどだ。鋲をうった扉から外に出てみれば、南風(「夏」の第1楽章が懐かしげに回想される)や北風や、ありとあらゆる方角からの風が吹き荒れ、闘いを演じている。しかしこれこそが冬の醍醐味なのだ。
弦楽のための協奏曲 ト長調 「アラ・ルスティカ」 RV151
- プレスト/II. アダージョ/III. アレグロ
特定の独奏楽器を起用しない、弦楽合奏と通奏低音という編成のための作品を(協奏曲やシンフォニアやソナタと銘打って)ヴィヴァルディは70曲ほど残した。これもその中の1曲だが、演奏時間がわずか4分弱という規模は異例なほど小ぶりである。
「アラ・ルスティカ」というタイトルは「田舎風」という意味を持ち、おそらく第1楽章におけるドローン的な持続音を伴う書式に由来する命名か。野を渡る一陣の風にも似た動機群が田園情緒を喚起する点は第3楽章も同様だ。第1楽章の意表をつく終結から(当録音ではチェンバロの絶妙な接続楽句を経て)流れ込む第2楽章は、サラバンド風のリズムで荘重な和声楽句が連なる、性格的対比に富む間奏曲さながら。
弦楽のための協奏曲 ハ長調 RV114
- プレスト/II. アダージョ/III. チャッコーナ(アレグロ・マ・ノン・トロッポ)
反復されるバス音形、および旋律的骨格の枠組みを従えながら変奏が展開されていくシャコンヌ(イタリア語でチャッコーナ)。この形式をコンチェルトに持ち込んで練達の筆致をヴィヴァルディが駆使した例の最たるものが、ここに収められた弦楽のための協奏曲ハ長調RV114の第3楽章である。鋭い付点音型と音階走句を対比させた第1楽章ともども、多彩なリズム書法が耳を飽きさせない(なお、第2楽章は譜面上、和音進行のみによるブリッジが記されているが、当録音はそこに補筆を加えた形で演奏している)。
演奏家プロフィール
新イタリア合奏団
I Solisti Filamonici Italiani
完璧な技巧と高い音楽性で超一流と折り紙付きの名アンサンブル、イタリア合奏団が、21世紀への新たな飛躍を求めてメンバーを一新、「新イタリア合奏団」としてスタートした。
メンバーは、ヴァイオリンのフェデリーコ・グリエルモをリーダーに、イタリアの著名オーケストラのコンサート・マスターやソロ首席奏者の経験者、国際コンクールの入賞者、有名なイタリアの室内楽グループ(ローマ合奏団、キジアーノ六重奏団)の元メンバーなどによって構成されている。レパートリーは弦楽六重奏から交響曲まで、またバロックから近代まで、指揮者を置かず、ソロもメンバーが交替で担当して演奏している。
これまでに多くの世界的アーティストと共演、その中には、アンドレア・グリミネッリ(フルート)、ハンスイェルク・シェレンベルガー(オーボエ)、ミラン・トゥルコヴィチ(ファゴット)、エマニュエル・パユ(フルート)、ミカラ・ペトリ(リコーダー)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)、ラドゥ・ルプー(ピアノ)、キャサリン・バトル(ソプラノ)、アンサンブル・ウィーン=ベルリンなどが含まれる。
地元イタリアでは、パユ、ルプーをゲストに迎えたツアーを行い、ヴィチェンツァのテアトロ・オリンピコでの「音楽のための人生」賞のレジデント・アンサンブルを務める。
スイス、ドイツ、フランスで毎年コンサートを開くほか、オランダ・ツアー、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイなど南米ツアー、ウィーン・ムジークフェライン、リンツ・ブルックナー音楽祭を含むオーストリア・ツアー、アジア・ツアーなどスケジュールが目白押しである。
フェデリーコ・グリエルモ ソロ・ヴァイオリン
Federico GUGLIELMO, Solo Violin
フィレンツェのヴィットリオ・グイ国際コンクール優勝者。トリノの国立放送管弦楽団のゲストコンサートマスター。デッカ、BMGなどからソロのレコーディング多数。
