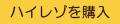デビュー25周年! ORIGINAL LOVE 田島貴男 スペシャルインタビュー

6月1日、デビュー25周年を記念したニューシングル「ゴールデンタイム」の配信がスタートしたORIGINAL LOVE。NHK・Eテレ「ニッポン戦後サブカルチャー史」で90年代音楽の特集が組まれた際、渋谷を中心に独自のチャートが形成されていた現象を紹介する文脈で大きく名前が取り上げられるなど、今再び注目を集めている。「渋谷系」と呼ばれたそのムーブメントは現在に至るまで錯綜した定義を持つが、ORIGINAL LOVEの首謀者たる田島貴男は「ミュージシャン主体で音楽を作って、それが結果的に動きになった」ものだったと語る。音楽が純粋に音楽であれた、その特別な時代と空間。当事者としてつぶさに見つめてきたからこその証言を、いまここにお届けする。
――今年に入って、ORIGINAL LOVE初期の4アルバム(『LOVE! LOVE! & LOVE!』『結晶』『EYES』『風の歌を聴け』)がハイレゾ化されました。新曲の配信もスタートしましたが、ここでいま一度ORIGINAL LOVEのルーツを紐解くべく、今回デビュー当時のお話を伺いたいと思います。
ORIGINAL LOVE前夜
――ORIGINAL LOVEってレコーディングバンドという側面はもちろんありつつも、肉体的なライブバンドという側面が強い気がするんですけれど。
田島 ORIGINAL LOVEの前身であるThe Red Curtainを始めた頃は違ったんです。僕は宅録少年でした。中学一年のときからずっとピンポン録音で曲を作ってて、高校卒業するくらいまでにストックが100曲くらいありました。大学に入って自分の曲を聴いてもらった友達の薦めもあって、バンドを組んで曲をお客さんに披露することになりました。しょっちゅうライブをやることによって、ライブの面白さに気づいて、ライブバンドにいつの間にかなってたんですよね。ただやっぱり曲をレコーディングしたものを人々に聴いてもらいたいという気持ちは同時にあったし、あの頃はいろいろやりたいことがいっぱいあって、楽しくて苦労は感じませんでした。とにかくあれもこれもやりたいという感じで。最初のORIGINAL LOVEのライブは自分で企画して、僕と木暮晋也ですけど、彼は彼でバンドを組んで。渋谷のライブハウス、ラママでやりました。
――その頃は木暮さんはロッテンハッツ(木暮の他、GREAT3の片寄明人、白根賢一らが在籍したバンド)ですか?
田島 いや、ワウワウ・ヒッピーズです。というかライブの日程が決まったとき、木暮はワウワウ・ヒッピーズもまだ組んでませんでした。僕のデモテープを持って行って、いろんなライブハウスを回るんだけど、ほぼ門前払い状態で(笑) ラママの、その頃の店長が、優しい人だったんで、お願いしますって言ったら、とりあえず貸切だったらいいよと。ライブハウスとしてブッキングはしないけど、貸し切りだったら貸すよって。 それでぜひやらせて下さいと。だからたぶん最初のライブはラママで出してるフリーペーパーあるじゃないですか、あれに「貸切」って出ちゃって。で、そういう感じで、お金もまったくなかったし、でも企画しちゃったもんだから、しかも木暮はまだバンドも組んでないしという状態で。「木暮はやくバンド組め」って言って、フールズメイト(音楽誌)にバンド募集の告知を出して。それで集まってきたのが白根賢一と高桑圭だったんですよね。
――すごいですね。
田島 Charaさんとかラブ・サイケデリコもやってる。あと僕の和光大の友達を紹介してワウワウ・ヒッピーズはその四人でやることになりました。僕はすでにThe Red Curtainを結成していました。準備期間は半年以上ありましたね。チケットは手売で、僕はひとりで60枚くらい売りましたよ。大学のキャンパスだとか、駅前で売ったりとかしました。結局満員だったんですよ。それで店長さんも「じゃあ、きみたち月イチで、やっていいよ」と言ってくれて、それで始まったんですよ。それから、うちでもやらないかって、他のライブハウスからも声がかかるようになっていって。
――それが何年くらいの話ですか?
田島 86年ですかね。
――宅録から始まり、その辺りで音楽家としての人格形成がされるわけですね。
田島 そうですね、とにかくパワーはありまくりで(笑) 髪型とか服装とかめちゃくちゃ変な格好してたんですけど、それでも気持ち悪がられながらもチケットを買ってくれる人はいてね。インディーで『ORIGINAL LOVE』ってアルバムを作るんですけど、あのサウンドはもうできてたんで、レコード会社の人も面白いって声をかけてくれて。
――それではここでようやくまずは1stアルバム。『LOVE! LOVE! & LOVE!』のお話をおうかがいしたいのですが2枚組ということもあって、ビジュアル的にも音的にも情報量に圧倒されたんですけど、なぜこういうデビュー作にして濃厚な作品ができたのでしょうか?
ORIGINAL LOVE黎明期~アルバム『LOVE! LOVE! & LOVE!』『結晶』『EYES』
田島 その前にORIGINAL LOVEの活動が5・6年くらいあったのでね。僕が18,19ぐらいからやり始めて、2年目か3年目くらいにピチカート・ファイブの誘いがあったんですね。なんで誘いがあったかというと、インディーレーベルであるミントサウンドレコードが作ったオムニバスアルバムに参加したんです。2枚作ったんですけども、1枚目はThe Red Curtain名義で2枚目はもうORIGINAL LOVEになってたかな。そこに小西さんも参加してたんですね。そこで小西さんに出会って、ピチカート・ファイブがソングライター兼ボーカリストを探してると。しかもレコーディングだけじゃなくライブ活動をするために……ということでライブ要員としても、僕がぴったりだと。あと僕の音楽を聴いて気に入ってくれてたということで、加入することになりました。
――『couples』(ピチカートファイブのCBS・ソニー第一弾アルバム)のを出す前の話?
田島 出してからですね。そこで僕が入って、でも専属契約だったんで、ORIGINAL LOVEは他のレコード会社と契約しちゃいけないと。でもピチカート・ファイブはレコーディングの知識とか、音楽の知識を学ぶためにとてもいい現場だと思っていました。そのときから二足のワラジの生活が始まったんですね。ORIGINAL LOVEは基本的にロックバンドですから。パンク、ニューウェイブから始まって、中学高校のときからずっと曲を書いていてそれをやる場だったんですけど、ピチカート・ファイブは小西さんのアイデアがまずあって、それに基づいてどういう作品を作るかっていう場所なんですね。だから全然曲の作り方、コンセプトが違う。ORIGINAL LOVEはレコードは出せないから書いた曲を、ライブハウスでやってたんですね。ピチカートで3枚やったあとやっぱりORIGINAL LOVEで自分の音楽を追求したいと。それで脱退して、ソニーの契約も切れたんで、じゃあORIGINAL LOVEでデビューしようと。だからめちゃくちゃ曲がたくさんあったんです。デビュー前にもう何十曲あったのかな、どの曲を選ぼうっていう状態でね。それとメジャーデビュー直前でメンバーチェンジがいろいろあったんですね。メジャーデビューする前と後とでORIGINAL LOVEのサウンドはかなり違います。メジャーデビューする前のサウンドにはキーボードがいない。ギターバンドだった。そんなこんなで曲がやっぱり絞り込めないから、2枚組にしようってことになって。
――それは誰のアイデアだったんですか?
田島 当時のマネージャーだった井出さんだったと思います。そのほうが面白いんじゃない?って。2枚組にすると値段が高くなるけど、それでもいいんじゃないかという感じで。
――『結晶』はもう次の年ですよね? 先行シングルも出て。ということはそこまでのストックがかなりあって?
田島 ストックというかアイデアがありましたよね。4枚目ぐらいまではありました(笑) あのころはいろんな音楽を浴びるように聴いてましたね……高校のときはパンク、ニューウェイブが好きだったんですけど、大学で東京に出てきて、中古レコード屋さんでバイトしたりいろんな音楽やってる人に出会ったり、小西さん、ピチカート・ファイブに関わることによって、パンク、ニューウェイブのアーティストはこんな音楽に影響されたのか、ロックの系譜はこうで、ポップスはこうでというふうに、なんとなくポピュラーミュージックが分かってきて、僕もいろいろ学びたいっていう時期だったんで、雑食的っていうか、いろんなところに手を伸ばした時期で、曲がいっぱいできちゃっていいたので。1stではとにかくストックを消化したかったんです(笑) 1stのアイデアっていうのは、僕はジャズが高校時代から好きで、郡山にいたときにジャズ喫茶にしょっちゅう行ってて。マイルスとかソニー・ロリンズとかを聴いてました。もちろんパンク、ニューウェイブも好きでしたけど、どっちかっていうとジャズの影響を受けたパンク、ニューウェイブってあるじゃないですか。リップリグ&ザ・パニックとかピッグバッグとか、ジョン・ルーリーのラウンジ・リザーズとか。そういうサウンドに影響を受けました。あと小西さんに出会って、ジョージ・シアリングを知るようになって。それをORIGINAL LOVEの曲にあてはめてやってみたりしましたね。あとモノクローム・セットも大学に入って友達から教えてもらって好きになりました。でも高校のころから好きだったバンドはギャング・オブ・フォーやザ・キュアーや、エコー&ザ・バニーメンとかでしたね。
――このころU2とかXTCなんかも出てきたりして。
田島 XTCはすごい好きでしたね。そういったアーティストたちに影響を受けて作った曲をライブでやって、1stアルバムのようなサウンド、いわゆる渋谷系的なサウンドが出来上がってきたんです。
――いろんな時代の最先端の音楽のごった煮てというか、そういう感じもあったんですね。
田島 そうです。そう言えば日本で最初にネオアコをやったのは僕だって言われてます。
――なるほど(笑)
田島 当時ネオアコサウンドをやってる人はまだ誰もいませんでした。ちょっと難しいからだと思うんですよね。4つぐらいコード覚えてガーッてやりゃいいって音楽でもないんで。アズテック・カメラみたいな音楽は、コードをある程度知ってなきゃできない造詣のある音楽なんですよ。僕はXTCが好きだったこともあっていろんなコードで曲を作るのが好きだった。ネオアコみたいな音楽をやり始めたのはフリッパーズ・ギターより先です。そう言った音楽に影響を受けて作った曲をベース、ドラム、ギター、女性コーラス二人という編成でやっていたのがデビュー直前のORIGINAL LOVEです。ところがデビュー直前でメンバーがほとんど総入れ替えになって、もうちょっと違うサウンドになった。そうなったのが1stの『LOVE! LOVE! & LOVE!』なんですね。デビュー前に作ったたくさんの曲をとにかくリリースして消化して、その上で次のいま自分が面白いと思っている音楽をやり始めたくて作ったのが2ndの『結晶』で。ヒップホップがサンプリングしていた、元のソウルミュージックなり、フュージョンミュージックなりのパーツがあるじゃないですか。あのパーツの音楽をいかに面白く生バンドで再構成して曲にするかっていうアイデアなんですよ。アシッドジャズをやってた人たちも、きっとそういうことだったと思います。それをポップス化するというか……でも前衛的なかっこいいことばかり考えてたわけじゃなくて、僕も小西さんもピチカート・ファイブにいるころから、ほんとにヒット曲を書きたかったんですから!(笑) どうやったらヒットチャートに上がるような音楽を作れるかっていうことは小西さんもすごく考えてたし、僕も考えてましたね。だから英語にしなかったわけだし。日本語で歌われる、みんなが共感できるポップスが一番つくりたかった、今もそうですけれども。昔の阿久悠さんの詞を読んだりとか……僕はどっちかというとサウンド志向でしたが、でもヒットチャートを上がるにはやっぱり詞が書けないといけないと思ってたんで。だからいろいろ自分で昔の歌詞を読んだりとかし始めて。そう言ったことがようやく上手くいき始めたのが「接吻」のころですね。
――「接吻」というシングルがあって、その前に『EYES』というアルバムが出て。そのころもヒットを狙ってはいた?
田島 もちろんですよ! 毎回狙ってましたよ。
――(笑)
田島 ORIGINAL LOVEが世間ですこしずつ話題になりはじめて、いいムードができてきてるんじゃないかっていう感じはありましたね。それが2ndのころで……ライブの動員が増え始めた時期です。「ヴィーナス」がブティックJOYのCMソングになって。あの曲はインディーのときからずっとやっていた自信のある曲でした。一番最初の大きなタイアップだったんじゃないかな。
――なるほど。
田島 3rdアルバム『EYES』での先行シングル「サンシャイン・ロマンス」はCMのタイアップが先にあった話です。歌詞とサビの部分を先に作ってくれと。CMタイアップ曲はそうやって作られることが昔から多いんです。その頃は独立して自分で事務所を作ってやり始めた最初の頃でして、その時まずやりたかったのが音楽をより本格化させたいと。日本のポップスの金字塔みたいな人たち、山下達郎さんだったり、ユーミンだったり。ああいった人たちが作り上げたサウンドのクオリティを僕も本格的に目指したいというのがあって、参加ミュージシャンも『EYES』の頃は、ちょうど過渡期なんですよね。井上富雄さんが2ndアルバムで離れて……最初からメンバーじゃなかったですけど、ほとんどメンバーみたいな感じでいたんですね。井上さんはバンドというものから少し距離を置きたいと。それでもすごく深く関わってくれたんですけど、でも一旦距離を置こうということになって。『EYES』ではいろんな人にサポートで入ってもらったんじゃないかな、渡辺等さんだったりとか、沖山優司さんだったりとか。
――名うての人たちですよね。
田島 そういう時期だったと思います。それで結局ベーシストのオーディションをして……『EYES』のあとに小松秀行が加入することになって。「接吻」がたしか小松のキャリアの最初なんじゃないかな。「接吻」のベースは小松です。
――93年とかですね。
シングル「接吻」
田島 そうですね。一瞬のうちにいろんなことが上手くいっちゃいました。その前には「sweat and sugar night」って曲がありますけど、あれは「接吻」の土台になったような曲ですね。「接吻」のタイアップの話をいただいたんですが締切が間近で、すぐ書かなきゃいけないと。でもうまい具合に、曲が1日とか2日くらいでできちゃった。作詞期間もなかったんですけど、仕事の移動中に書いたらできちゃったんです(笑)
――ああ、でもえてして名曲の誕生ってそういうもんだったりするって言いますよね。
田島 ええ。で、「この歌詞どうですかね?」 「ばっちりじゃないの」っていう。で、「接吻」の頃はまわりのスタッフが代わってたんです。新しいスタッフは、わりと歌詞についていろいろ言う人なんですけど、「接吻」については何も。全然ばっちりじゃないか! ということで。
――神が降りてきたというか。
田島 サビのメロディができた瞬間をいまだに覚えてますけど、タイアップの話をいただいて、来週までに作れ!みたいな感じになって、どうしようと思って、家に帰って2万円くらいのしょぼいエレキギターで「ふふふ~ん♪」で、できたみたいな(笑)
――ははは(笑)
田島 で、あーよかったみたいな。あの部分ができたらもう他のメロディは、あの部分が“呼んだ”んですよね。もうそこからはすぐできたという感じでしたね。
――手応えもその瞬間あって。
田島 うん、これはいけたな! と。でもそれはその仕事に対する、「いけたな」であって……こんなに長く聴かれる曲になるとは思いませんでしたね。初めてのゴールデンタイムのドラマタイアップだったんで、その仕事はクリアできたかなこの曲でという。
――達成感みたいな。
田島 はい。そういう実感でした。それがこんなに長くみなさんに聴いていただける曲になるとは……。
――カラオケでも世代を越えてみなさん歌ったことのある……
田島 最近は僕のことは知らなくてもこの曲は知ってるよっていう若い人もいて。そんな風になるとは全然予想もしなかったんですけど。ただいい曲ができたなという手応えはその時ありましたね。どちらかというとクライアント側の希望はもっと軽いタッチのお洒落な音楽を求めてたんですけど、僕としてはもうちょっとソウルミュージック的な、ディープな、セクシーな曲を書きたかったんですね。やっぱりネオアコとかパンクニューウェイブの音楽って、非肉体的なんです。でも当時、僕はそういうことをやってきた自分をのりこえたくてあえて肉体的なソウルミュージックをやらなければと思っていたし、ソウルミュージックがすごく好きだったし。大ヒットする音楽っていうのはそっちのほうだと思ってたし。ダイレクトに肌で感じさせるものがあるというか、そういう言葉なりメロディを持ってる音楽を目指してたんで。でも、実際の現場はとにかく「ヤバい! 時間ねーぞ! どうする!」みたいな感じだったのかな(笑)
僕の曲の作り方は、あんまりこの曲をモチーフにして……みたいな考え方ではないんですよね。どっちかというとギター弾きの曲の作り方で。ギターを弾きながら「メロディ浮かんでこないかなー」っていう風な作り方ってあるじゃないですか。あれでいまでもずっとやってるんで。渋谷系ってたとえばDJ的っていうか、レコードをいろいろ持ってて、この曲のこういう感じをこうしてっていう、編集的っていうか、そういう作り方ってあると思うんですが、僕はどっちかというとやっぱり楽器弾きの作り方で。
――だからおっしゃるような身体性というのが出てくるのかもしれないですね。
田島 そうですね。そこは決定的に違いますね。渋谷系の特徴と言われる「エディター的」というのは僕にはそんなにないんです。
シングル「朝日のあたる道」 アルバム『風の歌を聴け』
田島 それで話は前後しますが……より本格化したサウンドを作りたかったんですよね。いろいろオーディションをした中で小松のベースが圧倒的にすごかったんです。小松はポップスというよりはフュージョンやソウルの知識があるベーシストで、小松に「一緒にやりたいドラマーは?」って聞いたら「佐野康夫と俺はやりたい」って。で、佐野と小松と、木原龍太郎さんは残って。『風の歌を聴け』から小松と僕と龍太郎さんで三人で作ったんですね。だから(ベスト盤の)『SUNNY SIDE OF ORIGINAL LOVE』のときは過渡期ですね……メンバーがいろいろ代わって。
――では『風の歌を聴け』で初めて全国区になったという印象がご自身でもあって。
田島 そうですね。『SUNNY SIDE OF ORIGINAL LOVE』の後あたりにだんだん手応えを感じ始めて、『朝日のあたる道』で資生堂さんのCMタイアップがあって。アルバム「風の歌を聴け」はいろんなことが上手くいったというか、サウンドプロダクションも一から考え直せってなって、とにかく本格的な音を、絶対に作ってやるんだって、ミックスエンジニアの森岡さんもめっちゃ気合いが入ってました。全員がこだわってたんで、作る現場は大変だったんですけど(笑)
――制作期間もやはりそれなりにかけて。
田島 いや、制作期間は超短かったですね。一ヶ月ですから。とにかく忙しくなり始めた時期なんで。
――同時にライブもコンスタントにやっていたわけですもんね。
田島 そうですね。ただこのタイミング……『SUNNY SIDE OF ORIGINAL LOVE』でがっと盛り上がり始めたタイミングを逃すわけにはいかないと。
――ストックはもちろんあったと思うんですが……
田島 いや、その頃はもうゼロでしたよ(笑)
――ははは。そこから名盤を作るということになって。
田島 『風の歌を聴け』を作るまでにアルバムを4枚くらい作っているから、もうストックもなくて。でもそのときは気合いが入ってるから、それこそまた神が降りてくるじゃないけど、やってやるよみたいな(笑) この時やらなきゃどうするんだみたいな雰囲気もありましたし。スタッフも含めてみんな。で「The Rover」みたいな曲ができたり。でも僕ひとりじゃ一ヶ月じゃ無理だから、小松と龍太郎さんも1,2曲ずつ……共作の曲も入ってて。一番大変だったのは歌詞ですよね。曲を作る時間は一ヶ月あったけど、歌詞を作る時間はなかったんで(笑) 地獄を見ましたね。でも、こういうサウンドのアルバムを作ろうというヴィジョンは見えてたんで、とにかく自分たちの盛り上がりがあのアルバムを作ったなっていう。僕もそうだったし、ミュージシャンもそうだったし、エンジニアの森岡さんも、とにかくあのアルバムのこだわり方は大変なもんでしたね。「俺はもう絶対NEVEの卓でしか録らないから!」みたいな(笑) そうしてできたいい作品がオリコン1位にもなって。全部照準が合ったという感じですよね。
――曲単位でいうと、「朝日のあたる道」のエピソードなどは……
田島 あの曲もCMタイアップの話が先にあって、先に15秒のサビの部分を作って、全体を作る。あの曲だけ先に作ったんですよね、それも時間がなくて。スタッフの前でメロディーを口ずさみながら……あと歌詞ができなくてできなくて、現場の全員がとにかく気合いが入ってたんですよ。売れる直前の雰囲気ってあるじゃないですか。時間がないからなかなかいい歌詞ができなかったんだけど、頑張って僕が書いてこれどうですかって言ったらダメだこんなもん!って(笑)
――それは誰にダメ出しをされるんですか?
田島 そのときのスタッフです。でも自分でもダメだなとは思ってて(笑) あー時間もないしここまでかなという感じだったんです。でスケジュール仕切り直しになって。製作費どうしてくれるんだとめっちゃ怒られながら……(笑) 僕は自分で言うのもなんなんですけど、わりとタフっていうか、ワーカホリックというか……結構丈夫だと思ってるんですけど、そのときは一回だけ参っちゃって。熱だしてダウンしちゃって、医者に行って点滴打ってレコーディングも飛ばして。
――文字通り不眠不休という感じだったと。
田島 そうですね、スタッフも、ああやりすぎたかなって思ったかもしれませんけど(笑) 二週間くらいかけてまた歌詞書き直して。それで、もう一回書いてできたのが「朝日のあたる道」ですね。最初の歌詞でレコーディングした歌はボツになって。 とにかくレコーディングすること自体の費用がすごく高かった時代で、一日でうん十万円からですから。大御所の人ならともかく、僕なんてその頃はまだ新人扱いですからね。そこでダメなテイクとか録ったら、「お前バカヤロウ!」みたいな感じで。書き直しをして2回目に録ったのが完成形の歌詞ですね。プロデューサーは基本的に自分でしたんで、その間にアレンジもやったりしてるわけです。だから自分の体が五つくらいほしかった。普通プロデューサーやアレンジャーがいるわけじゃないですか? でも全部僕がやってたわけだから。
――自分の作る曲については自分が全部責任をもってアレンジすると。
田島 そうですね。『風の歌を聴け』に関しては小松とやった「時差を駆ける想い」と龍太郎さんとやった「二つの手のように」かな。あと「Sleepin’ Beauty」、これも小松と龍太郎さんとやったかもしれません。基本的にあのときは最初の1か月の制作期間で完全に打ち込みでアレンジしてマルチのデモを作ったんです。それはスタッフのアイデアだったんですけども、レコーディングスタジオ現場で訳わかんなくなったりしないように、マルチの段階でアレンジも最初から全部決めとけと。曲を作りながらアレンジも全部完成させてたんです、ホーンアレンジも弦のアレンジも。で、A‐DATという……
――懐かしいですね!(笑)
田島 でしょ? 自宅でレコーディングして打ち込みで作って、そういったアレンジは全部僕がやって。「The Rover」のホーンアレンジも全部できてました、打ち込みの段階で。それをそのままレコーディングスタジオで差し替えてくと。マルチでA‐DATのデータをSONYのPCM-3348にダビングして、3348にアナログレコーダーをスレーヴで回しました。で、リズム録りはアナログで。ダビングの時にあらかじめできてたホーンやストリングスのアレンジをそのままミュージシャンたちにやってもらって、ベースラインに関してもほとんどそのままやってくれと。「The Rover」もあのパターンで。佐野くんがすごいのは僕が考えたフレーズをそのまんまやるんだけど、全然違うものになるんです。すごいグルーヴになる。僕の予想の五倍ぐらいかっこいい。初めて「The Rover」を僕と小松と佐野くんでスタジオで鳴らしたときはもうガッツポーズでしたから。「きた!!!」みたいな。リズムを録り終わった段階で、今回のアルバムこれきたなと。だからアレンジは最初の一ヶ月でもうできてたわけです。
――まさに一人五役とかやってたわけですね。
田島 セルフ・プロデュースはピチカートのときから自分の曲に関してはずっとやってきたし、山下達郎さんもセルフプロでデュースだし俺もやりたいって思ったし、みんなも「田島、それやれ」みたいな。だからめちゃくちゃ忙しかったですよ。大変でしたね。客観的な判断基準がないわけですし。
――誰かに任せたほうが楽だという風には思わなかったんですか。
田島 思いましたよ。いま思うとね。あんな倒れるまでなんでやったんだろうって。
――(笑)
田島 あのレコーディングはとにかく超大変で。ピチカートのときからアルバムレコーディングはいつもめっちゃ大変でしたね。とにかく全体力全ての力を使いきって。
――年齢的には……ぎりぎり20代くらいの感じですか。
田島 風の歌が29歳ですね確か。「接吻」が28歳だから。
――若かったからできたってところもあるかもしれないですね。
田島 ですね。しかもプロモーションも僕ひとり出ていって、取材受けたりとかするわけですから、超大変だったけど楽しかったですね。その大変さが。自分の音楽を思う存分やれてる時期だったし、いまでもやれてますけど、それまで夢として「こういう風に音楽やりたいな」って思ったことが実現していった喜びもあったんで。だからそういう馬鹿力みたいなもんが発揮できたっていうかね。
――「朝日のあたる道」はチューブラー・ベルが入ってるじゃないですか。
田島 あれは小松が。あらかじめメロディーラインは出来てて、チューブラー・ベルのミュージシャンを呼んでもいいんだけど、小松できるこれ? って言ったらやるやるって言って(笑) なんで入れたかっていうのは、フィル・スペクターとか昔のモータウンのサウンドが好きだったから、ああいうイメージで。だいたいチューブラー・ベルが入ってるじゃないですか。僕のポップス感覚というのは60年代のスペクターサウンドとか、モータウンサウンドが基準になってるところがあって。ビートルズだってそうなわけだし。だから自分がシングル曲作るってなると、なんとなくそういうサウンドになっていくんですね(笑) どこかしらモータウン的な。
――でもリズムの跳ね方とか、そういう影響を受けられてるんだなっていうのは。
田島 そうですね。だから「朝日のあたる道」に関しては、スティービー・ワンダーとモータウンみたいな。あとビーチ・ボーイズ……今考えるとそうなのかなあって感じがしますけど、当時はそんな余裕はないですよ。とにかく時間がないし、やるぞやるぞという感じで。
――血肉となってインプットされてたからそういうとき出てくるってことですよね。
田島 聴く人がこれはビーチ・ボーイズで……とか言うんですけど、現場ではもうそんなこと考える余裕ないっていうか。無我夢中で作ってたわけですよ。
――「The Rover」とかやっぱり気迫がすごいじゃないですか。そういう意味では当時の衝動が全部入ってるとか。
田島 スライ&ザ・ファミリー・ストーンが好きで、そういう曲を作ってみたかったんですよ。リズムボックスで始まって、それと同時にドラマーがドラムを叩くっていう。スライがやってた「暴動」とか「Fresh」のアイデアをやってみたかった。サビのコード進行とかホーンのラインも、スライを意識しました。ホーンセクションのレコーディングの時、数原晋(日本を代表するトランペット奏者)さんに褒められて嬉しかったです。ホーンセクションレコーディングが終わったときに、「ホーンセクションを上げたツーミックスを作ってくれ、俺帰って聴くから」と言ってくれて。嬉しかったですね。「The Rover」はアルバムの中でもキー曲というか、象徴するような曲ということで託して作りました。「LET’S GO」(『EYES』収録曲)の延長上にあるっていうか。「LET’S GO」はギル・スコット・ヘロンの影響があって作った曲ですけども。そのさらに延長上にあるのが「The Rover」なのかなというのが今思い起こすとありますね。
おわりに
――最後に、当時を振り返ってなにか一言あれば。
田島 あの当時はミュージシャンが作りたいと思ったことを実現できてた時代で。なんだかんだ怒られながらも自分の我を通せてたというか、それが売れてた時代で。そう言った現象があとから渋谷系って言われるようになったのかなと。僕と同じように言われてる人たちっていうのはおそらく同じようにセルフプロデュースで、自分の作りたいものを作ってた人たちなんですよね。小西さん、小山田(圭吾)くん、小沢(健二)くん……それまでのアーティストはプロデューサーやディレクターがいたりしていろいろああだこうだって作りこんでいく音楽だったんですけど。僕らが作った音楽ってのはミュージシャンがほとんど全部決めてたというか。最初の2枚は井出さんがビジュアルを作ってくれたというのはありますけど、サウンドに関してはやっぱり僕が作っていたし。ああいったことが実現できてそれがヒットしたのがうれしかったし。渋谷系とか言われるようになっていろんな誤解や面倒くさいこともあるんですけど。ミュージシャン主体で音楽を作ってそれが結果的に動きになったというのが、後から考えるとうれしいことだなと思いますね。でも自分のアーティステックな欲求を満たすためだけにやってたかというと、そういうことではなくて。僕はとにかくポップスを作りたかったんだから! 「田島さんの作ってる音楽は“渋谷系”なんですよね」「違います。僕の作ってる音楽はポップスです」と、ずっと言ってるんですけどねえ……。
――ははは。
田島 それはいわゆる売れ線ってことではなくて、音楽的なポップスていうのかな、ビートルズだったり、バカラックだったり、スティービー・ワンダーだったり。単純にいいポップスを作ってヒットさせたいと思って、そのためにはどうしたらいいんだということを考えました。でもその代わり売れるためにダサいことをやるってことではない。音楽としていいクオリティのものを、なおかつ普遍性のあるものをってことばかりを考えてたんです。その時もそうだったし、今現在もそう思いながら、曲を作り続けていますよ(笑)
デビュー25周年記念 ニューシングル!

『ゴールデンタイム』
初期の傑作4タイトル ハイレゾ配信中!