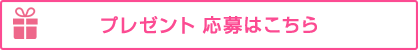伝説の「神」ドラマー、村上“ポンタ”秀一インタビュー! ~音楽生活45周年を記念して~

日本の音楽界において神話的存在にあるドラマー・村上”ポンタ”秀一のデビュー45周年を記念して、日本最高峰のプレイヤー達を招き、2018年4月6日に中野サンプラザで開催されたコンサートのハイレゾ音源がmora独占先行配信スタート 。
ここでしか聴くことが出来なかった名曲プレミアム・セッションを、ハイレゾ音源でぜひお楽しみください。
音楽境地 ~奇跡のJAZZ FUSION NIGHT~ Vol.1+Vol.2
「音楽境地 ~奇跡のJAZZ FUSION NIGHT~ Vol.1+Vol.2」ハイレゾ音源を、まとめて(アルバム)ご購入頂いた上でご応募してくださった方の中から抽選で3名様に「村上”ポンタ”秀一 サイン入りグッズTシャツ」をプレゼント!
応募期間 2018年4月27日(金)0:00 ~ 5月31日(木) 23:59:59
※プレゼントの応募期間は終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました!
「音楽境地 ~奇跡のJAZZ FUSION NIGHT~ Vol.1+Vol.2」の分割パッケージはこちら
■音楽境地 ~奇跡のJAZZ FUSION NIGHT~ Vol.1
■音楽境地 ~奇跡のJAZZ FUSION NIGHT~ Vol.2
以下、今作に収録のライブ直前に行われたインタビューです。(2018/3/26初出)
日本屈指のセッション・ドラマー、村上“ポンタ”秀一。氏が1970年代、赤い鳥に参加してから今年で音楽生活45周年を迎えるのを記念し、4月6日、中野サンプラザにて、ゆかりの深いミュージシャンたちを一堂に集めて“一夜限りのスーパー・プレミアム・セッション”と銘打ったライヴ『The 45th Anniversary 音楽境地~奇跡のJAZZ FUSION NIGHT』が催される。去る2月には、自身がプレイを刻み込んだ80年代名盤の1曲ごとについてマニアックに語った著書『続・俺が叩いた。~ポンタ、80年代名盤を語る』(リットーミュージック刊)を発表した氏だが、今回のインタビューでは、45周年ライヴで演奏される予定の、高中正義、渡辺香津美、角松敏生、大村憲司の4氏にまつわる楽曲の当時のレコーディング・エピソードや共演ステージでの想い出などを、『俺が叩いた。』風にちょっとマニアックに振り返っていただいた。
インタビュー:村田誠二
Theme 1:高中正義「黒船」 ~当時、俺ら界隈のミュージシャンはみんながみんなを意識してたんだよ~
――まず、45周年で共演するフロントマンの1人、高中正義さんとのセッションでは、サディスティック・ミカ・バンドの「黒船」(『黒船』/1974年より)や「Thunderstorm」(『虹伝説』/81年より)、そして「BLUE LAGOON」(『JOLLY JIVE』/79年)が予告されていますが、そもそも高中さんとのつながりは、70年代、赤い鳥時代からですよね?
ポンタ 赤い鳥って当時ものすごく忙しいグループで、平日どこでコンサートをやっていても、土曜日には必ず赤坂のTBSホールでレギュラー出演(TBSラジオ「ヤングタウンTOKYO」の公開放送)があったの。毎週東京に帰ってこなきゃいけないって、けっこうハードだったんだけど、その番組はいろんなバンドが出てたし、すごく中身が濃かったんだよ。そこで、フライドエッグっていう成毛(滋)さんとつのだ☆ひろのバンドと一緒になったことがあって、そのとき“ベース”を弾いてた高中に初めて会ったんだよ。

――その後、高中さんとポンタさんは、井上陽水さんのアルバム『氷の世界』(73年)の「はじまり」と「桜三月散歩道」の2曲にクレジットされています。
ポンタ そう、なぜかスタジオ・ミュージシャンの高中とね。当時はポリドールがスタジオ・ミュージシャンを抱えていて、俺は深町純とのつながりでスタジオ・ミュージシャンとして呼ばれたんだ。このときも一緒に演奏した記憶はないからダビングだと思うけどね。だから、ちゃんと交流がはじまったのはやっぱりミカ・バンドとサディスティックスだと思うんだ。実際、サディスティックスでは(後藤)次利のセクションは俺が呼ばれて、(高橋)幸宏に代わって俺が叩くことが多かったから。そこには当然幸宏も遊びに来てるしね……それもビクターの4Fだったと思うな(註:取材はビクター・スタジオの1Fで行いました)。とはいえ、当時その界隈のミュージシャンは、みんながみんなを意識してたんだよ、「アイツは今度どういうことをやるんだろう?」とかって。
――『黒船』は74年のアルバムですが、当時ポンタさんの耳に入ってましたか?
ポンタ いや、まったく記憶にない。ちゃんと聴いたのはずっと後だよ。
――この当時、ピンク・フロイドやプロコル・ハルムを手がけていたクリス・トーマスをプロデューサーに、レコーディングでは彼がフロイドの『狂気(Dark Side of The Moon)』などで使った、録音してはテープを切ってつなぐという編集手法をとったようですね。
ポンタ 日本のレコード業界ではハシリだよね。イギリスの連中はピンク・フロイドをはじめ、そういうことをしょっちゅうやっていたわけだから。で、トノバン(加藤和彦)はそういうの、ものすごく早かったんだ。俺がテープを切ったり貼ったりっていうのをよくやったのは、このアルバムとはちょっと趣旨が違うけど、深町とやったソロ(『イントロデューシング・ポンタ村上~驚異のパーカッション・サウンド!!』/76年)だよ。実際、テープを切ってつなげるっていうのは日本のエンジニアが世界一だったからね。スタジオにはカミソリの刃と白いテープが必ず置いてあったのをよく覚えてる。こういう細かい作業、ニューヨークの連中は苦手なんだよね(笑)。
――アルバムの中で「黒船」は、“嘉永六年六月二日”から“六月四日”までの三部構成の組曲になっていますが、まず最初を飾る「黒船(嘉永六年六月二日)」の冒頭の不自然な(!?)拍のドラム・フレーズが、まさにテープを切って貼ったものだそうですね。
ポンタ そうなんだよな。そのイントロ、去年12月のクリスマスにやった高中のライヴ(Christmas Special Live 2017“まさよし この夜”)では、わざと間違うっていう小芝居をしたんだけど(笑)。実際あのフレーズはヘンだよ。(テープの)貼り方がおかしいよな、妙な拍だし。
――曲中は9/8拍子になるんですが、ライヴでも、あのフレーズを丸ごと覚えて叩くんですか?
ポンタ いや、俺はイントロだけは6/4(拍子)で考えてる。要するに3拍子ってことよ。だから、曲中に入ったら、俺と次利は9/8拍子に切り替えるから。
――やっぱり冒頭のドラム・フレーズだけは、ライヴでもオリジナルのテープ編集の“いびつさ”を少し意識しているんですね。
ポンタ (オリジナルは)絶対テープをちょっと短く切りすぎたん思うな(笑)。もちろん、それがヘンな変拍子に聴こえて面白かったんだけどね。
――近年の高中さんのライヴでは、宮崎まさひろさんとのツイン・ドラムなんですよね。
ポンタ そう、だから「黒船」も“ツイン・ドラム”としてフレーズを考えてるから、宮崎がずっと16をキープしつつ、俺がアクセントだけを強調して叩いたりしてるよ。
――続く「黒船(嘉永六年六月三日)」のファンキー・パートでも、ライヴでは2人のコンビネーションがナイス・グルーヴしていますね。
ポンタ 一応“ドッパァーン・ウドッ パーン”っていうアクセントだけ決めておいて、あとは自由にやってるよね。
――今回、45周年ライヴでは「黒船(嘉永六年六月四日)」のインスト・バラードだけを組み込んでフィーチャーするそうですね。
ポンタ それは高中の意見なんだ。昔、「READY TO FLY」って曲と「黒船」をつなげるときにPart 3(六月四日)だけを使ったのが面白かったんじゃないかな? 実際、Part1(六月二日)もPart 2(六月三日)も、当時こういうアイディアをリスナーが“なんかヘンだな”と思って面白がったかもしれないけど、聴いてると、本人達が自分のパートを必死でやってるっていう印象を受けるよね。もちろん“プログレ”ってそういう面白さもあるんだけどね。
Theme 2:渡辺香津美「遠州つばめ返し」 ~富士山をバックに東海道を飛脚が走ってる、そんな“和”なイメージ~
――さて、続いては渡辺香津美さんとのセッションで予定されている「遠州つばめ返し」についてうかがいます。
ポンタ この曲は、山下洋輔さんが古典落語の「寿限無」を曲にしてしまったのをインストでやってしまったようなもんだよ。こんなメロディ、とうてい譜面には書けないから、そのまま“歌”として覚えてしまうしかないっていう点でも同じだしね。俺はもう(この曲を)やりすぎてて、いつ頃のって細かく質問されてもまったく記憶にないけど、MOBOIII(渡辺香津美、グレッグ・リー、村上“ポンタ”秀一のトリオ)の全米ツアー(85年8月に全米18ヵ所公演)では毎日やってたし、香津美とデュオでも頻繁にやったし、“MOBOバンド”(ツイン・ベース/ツイン・ドラムにキーボード、サックスなどが入った大所帯バンド)でもやってるしね――それは『桜花爛漫』(85年)っていうライヴ・アルバムに入ってるよ。
――アルバム『MOBO』(83年)のスタジオ録音では、リズム体はマーカス・ミラー(b)とオマー・ハキム(d)なんですよね。
ポンタ それすらもあまり記憶にないけど、俺はやってて一番面白いのはデュエットだな。いわゆる“対話”だよね。途中でどこ行こうが何しようが(テーマに)帰ってこられるしね。途中2人とも顔を見合わせてすらいないから。そういう音楽の最たるものだよね。丁々発止って言葉がぴったりな音楽。リズムが10種類くらい変わったり、けっこうスリリングで面白いことやってるから。当然、何やったかなんてイチイチ覚えてないけど、いい対話ができたなと思うときは、なんか勝手に動かされてるみたいな、もう上手いとかヘタとかいう範疇を超えて“遊んでる”んだ。

――「遠州つばめがえし」というタイトルもあって、この曲には映像的なイメージがあるそうですね。
ポンタ この曲、たぶん香津美が新幹線に乗ってる間にピューって書いちゃったんだと思うよ。本当につばめを見たんじゃない? で、佐々木小次郎の“つばめ返し”だよ。長い刀でピシッと斬って、ハネだけパサ~って落ちてくるみたいな……ホントにそういう曲だもん。香津美は今でもそうだけど、そういう遊び心があるんだ。俺の中では、東映の時代劇で富士山をバックに、穏やかな日和の中、東海道を飛脚が一生懸命走ってる、みたいなイメージがあるのよ(笑)。そういう“和”のイメージは、仙波師匠(仙波清彦/d)が代表してるようなところもあるからね。邦楽囃子仙波流の家元だからね。
――MOBOバンドでは、仙波さんとはドラム+パーカッションではなく、ダブル・ドラムでしたね。
ポンタ そうだね。最初におおまかなことを決めるんだけど、その基本形の中でお互い自由にどんどん変化していく関係だよね。“あなたにも、ポリシー、あげたい”みたいな(笑)。
――そのギャグは若い人にはわからないですね(笑)。そもそもツイン・ベースとツイン・ドラムという編成のMOBOバンドはどういうバンドでしたか?
ポンタ 渡辺建ちゃん(b)はルートと1つのパターンでしっかり固めて、その上でグレッグ(・リー/b)が好きに弾きまくるっていう関係も良かったし、仙波さんと俺は、さっき言ったように、着かず離れず、自由に面白いことやってる――そういう意味では人選からして香津美の計算なんだよ。特に建ちゃんなんて本当に真面目な人だから、ツイン・ベースだってことを考え抜いてプレイしてたと思うしね。それこそ譜面を書いてたんじゃないかっていういうくらい、そういうベーシストだから。それに(橋本)一子(p/voice)とサックスのみっちゃん(沢村満)の味付けが最高で、それも見抜いた上での人選だからね。俺らはその香津美の計算の上で踊らされているわけ(笑)。
――ライヴ盤の「Σ」でも、橋本一子さんの演じっぷりがすごいですね。
ポンタ 最高でしょ(笑)。ライヴのときのSMの女王のコスチューム、俺、大ファンだったから。六本木ピットインで、その格好でお客のテーブルに上がっちゃうんだから(笑)。カッコいい~~一子!みたいな感じ。でもその次にピアノにパッと座るとキレ~イなボサノヴァを弾くわけ。そのギャップがまだいいんだな。
Theme 3:角松敏生「OSHI-TAO-SHITAI」/「RAMP IN」 ~角松専用のスネア・ドラムがあるくらいドラムにウルサい~
――さあ今度は、角松敏生さんの「OSHI-TAO-SHITAI」や「RAMP IN」についてうかがいます。「OSHI-TAO-SHITAI」は、アルバムとしては87年発表のインスト・アルバム『SEA IS A LADY』の収録曲ですね。
ポンタ これは角松がインスト・アルバムを作りたいってことで、もうやろうやろう!って。この時期にミュージシャンが一番団結するんじゃないかな? みんなけっこう気合い入ってたからね。角松も、もちろんヴォーカリストなんだけど、基本的には“ミュージシャン”なんだよ。口では“僕は(大村)憲司さん比べると……”とか言うんだけど、でもインストゥルメンタルがやりたいって、そういうところが俺は面白かった。そもそもアイツはミュージシャンが好きなんだよ。ニューヨークの連中といつも交流してたりするのもそうだしね。日本にはあまりそういうタイプいないから。
――歴代のミュージシャンを見ると、スティーリー・ダンと同じくらいドラマーにウルサいんじゃないですか?
ポンタ ウルサいよぉ~(笑)。GROOVE DYNASYってイベント(林立夫が発起人となり、ポンタ、沼澤尚、村石雅行、真矢の5ドラマーがホストとなってさまざまなゲスト・ヴォーカリストを迎えておこなったライヴ・イベント)で、角松がゲストの年に、スティーヴ(・ガッド)とレコーディングした曲(「浜辺の歌」)を完コピでやってほしいっていうリクエストがあったんだけど、「いいよ~」って、リハでは完璧にやっておいて、いざ本番で(ドラムだけになる場面で)俺、立って踊ったの(笑)。そうしたらアイツ、ホントに怒ったよね……。終わってから口聞いてくれなかったもん。俺はそういう予定調和を崩すの、大好きなんだけどね(笑)。話が逸れちゃったけど、角松がドラムにウルサいのは、特にリズムのパターンとか、ハイハットとスネアとキックの組み合わせ、あとは音色だよね。特にバラードに関してスネアの音色はむちゃくちゃウルサくて、角松用のスネアがあったくらいだから。
――それが、材質がコパーの14×5インチと14×6.5インチのスネア・ドラムですね。
ポンタ もちろん他の歌手でもいっぱい使ってるけど、コパーの5インチ、6.5インチって言ったら、角松の顔が同時に思い浮かぶからね。今回の45周年のイベントでもやる予定の「RAMP IN」が、まさに14×6.5インチで、よくレコーディングでも「角松君の“あの曲”で使ってるスネア、持ってきてください」なんて言われたよ。あと、“スネアの音=時代の音”っていう時代だったんだよ。まさにAORだよね。TOTOだって、ジェフ(・ポーカロ)の音がなかったらTOTOじゃないもんね。で、やっぱり俺は“AORドラマー”なんだよ。

――「RAMP IN」は、これまでの振り返りインタビューでもたびたび言及される、ポンタさんの中で特に思い入れがあるようですね。レコーディング・メンバーも珍しいですし。
ポンタ メンバー選びも、角松はシブいのよ。自分と同い年くらいのミュージシャンだと“味”が出ないと思ったんじゃない? やっぱりピアノの渋井博さんとかギターの幾見(雅博)とかこの曲に合ってるもん。
――ストリングス・アレンジも大谷和夫さんですね。
ポンタ ストリングスを大谷さんに頼んでるっていうのが、またシブいよね。角松は、いろんなアメリカのミュージシャンを、年代を問わずかなり広範囲に聴いてるからね。それも(山下)達郎なんかの影響だと思うけど。
――では「OSHI-TAO-SHITAI」に話を戻しましょう。この曲は冒頭からものすごいシンコペーションの嵐ですよね。
ポンタ 角松独特のシンコペーションのアレンジっていったら、ひとつ色が決まっちゃうから、それを突き詰めていくっていう美学だよね。でもそれが飽きないんだ。「SEA LINE」って曲でも、ずっとシンコペーションなんだけど(と言ってメロディを歌い始める……)、1ヵ所だけクわない(シンコペーションしない)ところがあるわけ(笑)。俺がそこをクッちゃったときの青木(智仁/b)の顔っていったらなかったなぁ~、冷ややかな「何やってんだ、コイツ」みたいな目でね(笑)。でも俺はこういう性格だから、次も同じことやってやるんだ(笑)。
――同じことを2回やれば間違いじゃなくなりますからね(笑)。「OSHI-TAO-SHITAI」の冒頭は、シャープなシンコペーション・フレーズの嵐ですが、実はいろんな空白があって、そこをどう演技するか、角松さんの歴代ドラマーで違いがあります。ポンタさんはこの空白を埋めないですよね。
ポンタ 俺はそこ、埋めたくないんだ。(角松の)35周年の横浜アリーナのライヴのときでも、玉ちゃん(玉田豊夢)とか(山本)真央樹は埋めるのがすごくうまいんだよ。でも「隙間を空けっぱなしでやってみたら面白いんじゃない?」ってやってみると、意外と難しかったみたい。この曲のオリジナルのエンディングなんてスッカスカでやってるからね。普通だったら“ババァ~ン!!”っていうキメの前なんて絶対埋めるけど、あえて埋めないのがいいんだよ。
――そして、激しいシンコペーションのイントロを通過してAメロが終わったところで、ポンタさんのトレードマーク的なフレーズ“ドバラド”に近いユニゾン・フレーズがありますね。
ポンタ そこは青木と“ドバラドウパッ!!”みたいなフレーズを入れたいって、ユニゾンで毎回同じフレーズをやってるんだ。このフレーズは、“ドバラドウパッ!!”って(最後のパッを)シャープにやったら面白くないの。“ドバラドウベェ”みたいにやっておいて、その後の“ンパッパッパッ!!”(をシャープにして)でスピード感を出すわけ。そこがこの曲の1つの醍醐味でもあるよね。
――“ドバラドウパッ”より、もっとたくさんの音が聴こえますが。
ポンタ 完全なユニゾンじゃなくて、俺と青木でちょっとズレてるのがまたいいんだよ。
Theme 4:大村憲司「TOKYO ROSE」 ~憲司が素養として持っていたオリエンタルな景色~
――では最後に、45周年ライヴではトリビュート・コーナーがありますが、そこで大村憲司さんの「TOKYO ROSE」をピックアップされましたね。この曲はポンタさんと憲司さんの“憲ポン・バンド”の最後期の曲ですね。
ポンタ ホントに後期だよね。「TOKYO ROSE」が音源として残ってるのは(97年4月26日の)六本木ピットインのテイク(大村憲司『ベスト・ライヴ・トラックスII』)と、神戸チキンジョージでやった25周年ライヴのテイク(大村憲司『レインボウ・イン・ユア・アイズ~ベスト・ライヴ・トラックスVII』)だけだよね。

――今回、配信する「TOKYO ROSE」は、97年4月12日のチキンジョージ音源をハイレゾ・マスタリングした、配信限定アルバム『ヴェリィ・ベスト・ライヴ・トラックス』からのものですが。
ポンタ 憲司のトリビュートをするとなったら、やるべき曲はありすぎるわけで、ホントは「BAMBOO BONG」だってやりたいんだよ、でもお客が何やってんだかわからなくなっちゃうし(笑)、そこで俺が妙に印象に残ってるのが「TOKYO ROSE」なんだ。当時、憲司が曲を持ってきたとき「何、この曲。どういう心境の変化なの?」って聞いたくらい、憲司としては珍しい曲だと思った。ちょっとオリエンタルな匂いもして、イントロなんて「チャイナタウンか?」と思ったくらい。憲司は、戦後のFENの、窪田ひろ子さんのDJとか当時ラジオから流れてきた音楽みたいなイメージが……とか言ってたのを覚えてる。洋楽なんてそんなにあったわけじゃないそういう時代とか、当時それをそれを聴いてたリスナーとか、そういうものをひっくるめた景色ってことだと思うけど。
――憲司さんがプロデュースしたポンタさんの82年のジャンボ・シングル『PADANG RUMPUT』でも、まさにタイトル曲がオリエンタルな響きですよね。
ポンタ 俺の中でパッと最初に出てきたイメージは香港のポン引きだけどね(笑)。冗談はさておき、もともとオリエンタルな部分って憲司の素養としてあるもので、当時イエロー(YMO)をやった中でも、そういう部分が出てきたんだと思う。ただそういうメロディの中に、やっぱりロンドン・ポップが残ってるんだよ。
――憲ポン・バンド結成まで、憲司さんとはしばらく離れていたんですよね?
ポンタ で、憲司に「ポンタ、久しぶりにライヴやろうか?」って言われて始まるわけだけど、その前に房之助と憲司と吉田建とでブルース・バンドをやったこともあるんだけど、それはまた水を得た魚だったよね。「やっぱりこの人はうまいな」と思ったもん。
――最近も「憲司さんがいないことを痛感する」と仰っていましたね。
ポンタ 今回のライヴでこの曲をCharに弾いてほしいと思ったのは、(近藤)房之助とCharと俺のツアーに憲司を呼んで、沖縄の空港で別れたのが最後だったっていうのもあったからだけど、ホントに、これだけギタリストがいるのに、今でもいざってときに必ず憲司を思い出してしまうわけよ。いいときにいなくなって、ヒキョーだよな!
ポンタさん関連
・村上“ポンタ”秀一 ライブスペシャル「音楽境地」~奇跡のJAZZ FUSION NIGHT~ – オフィシャルサイト
盟友・大村憲司さん関連